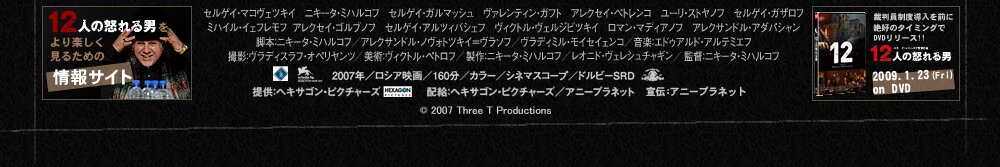1957年にベルリン国際映画祭で金熊賞に輝き、アカデミー賞3部門にノミネートされた『十二人の怒れる男』はレジナルド・ローズの脚本をもとにしている。この脚本をかつてシュキンスキー演劇学校で舞台化したことのあるニキータ・ミハルコフは、8年間のブランクを経て、21世紀のロシア状況を反映させる題材として選んだ。オリジナルを尊重しながらも、現代ロシア(現代世界)に闊歩している拝金主義、モラルの喪失、民族差別を浮かび上がらせる展開に仕立て、さらに現代にふさわしい結末まで生み出してみせた。ミハルコフ自身が“まったく新しいオリジナル作品になった”と語っているのも頷けるところ。
1957年にベルリン国際映画祭で金熊賞に輝き、アカデミー賞3部門にノミネートされた『十二人の怒れる男』はレジナルド・ローズの脚本をもとにしている。この脚本をかつてシュキンスキー演劇学校で舞台化したことのあるニキータ・ミハルコフは、8年間のブランクを経て、21世紀のロシア状況を反映させる題材として選んだ。オリジナルを尊重しながらも、現代ロシア(現代世界)に闊歩している拝金主義、モラルの喪失、民族差別を浮かび上がらせる展開に仕立て、さらに現代にふさわしい結末まで生み出してみせた。ミハルコフ自身が“まったく新しいオリジナル作品になった”と語っているのも頷けるところ。
撮影期間は2ヶ月を要したが、ミハルコフは事前のリハーサルを綿密に行なうことを主張。12人に選ばれた俳優たちがすべて揃うことがキャスティングに際しての条件となった。撮影期間中は他の仕事と掛け持ちをせずに、全身全霊をもって役に入り込むことを望んだ。ただひとり、ヴァレンティン・ガフトのみが舞台が外せずに例外となったが、その間もミハルコフはスタッフ・キャストとリハーサルを行なった。リハーサルでシーン、エピソードを分析し、撮影は“順撮り”。ストーリーに沿うかたちで遂行された。そのなかには陪審員1番に扮したセルゲイ・マコヴェツキイによる10分間のモノローグを、ワイドショットのワンシーンで撮影する試みも織り込まれている。ミハルコフはある意味では俳優たちに舞台的な緊張感を与える手法を選択したのだ。12人の葛藤が展開する場所が体育館に限定されているので、監督はチェチェンの少年の悲惨な記憶をフラッシュバック的に散りばめる。この部分は最後にクラスノダール地方アデルビーブカ村にセットを組んで数日に渡って撮影された。

音楽を担当したエドゥアルド・アルテミエフはミハルコフの盟友。心理的サスペンスのドラマを盛り上げる道具のひとつとしての、音楽の在り方を熟知しているアルテミエフはシンフォニックな旋律のなかに叙情性をたたえ、ときに戦闘シーンとの効果音を織り込みながら、映画のテーマである“人生についての考察”をいっそう深める役割を果たしている。
陪審員7番、カフカス地方出身の外科医の台詞のなかに登場するピロスマニとは、グルジア出身の19世紀末‾20世紀初頭の画家のこと。ゲオルギー・シェンゲラーヤによる映画『ピロスマニ』でその軌跡が描かれている。パラジャーノフは『火の馬』や『ざくろの色』などの映画監督で画家のセルゲイ・パラジャーノフ、ショタ・ルスタヴェリは12世紀の詩人のこと。