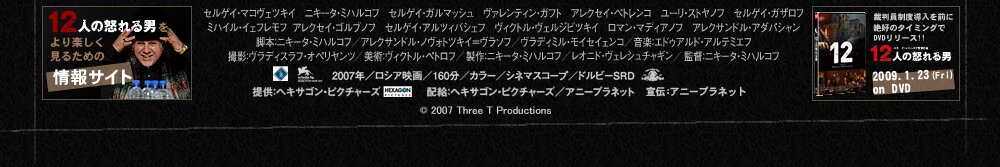1957年に登場した『十二人の怒れる男』は社会正義を謳いあげた法廷ドラマとしてアメリカ映画史に燦然と輝いている。もともとはテレビ番組「Studio One」のドラマとして脚本レジナルド・ローズ、監督シドニー・ルメットのコンビが生み出したもの。緊迫感に溢れた展開と計算されつくした演出が、陪審員それぞれのキャラクター設定の妙とあいまって、なによりも製作された時代の風潮が色濃く反映される構造になっている。1997年にウィリアム・フリードキンが「12人の怒れる男/評決の行方」として再びテレビ映画化するなど、<法廷ドラマの原点>といわれる所以で、この1957年作品は世界中の法廷ドラマに多大の影響を与えている。
1957年に登場した『十二人の怒れる男』は社会正義を謳いあげた法廷ドラマとしてアメリカ映画史に燦然と輝いている。もともとはテレビ番組「Studio One」のドラマとして脚本レジナルド・ローズ、監督シドニー・ルメットのコンビが生み出したもの。緊迫感に溢れた展開と計算されつくした演出が、陪審員それぞれのキャラクター設定の妙とあいまって、なによりも製作された時代の風潮が色濃く反映される構造になっている。1997年にウィリアム・フリードキンが「12人の怒れる男/評決の行方」として再びテレビ映画化するなど、<法廷ドラマの原点>といわれる所以で、この1957年作品は世界中の法廷ドラマに多大の影響を与えている。
この<法廷ドラマの原点>に新たに挑んだのは、『機械じかけのピアノのための未完成の戯曲』や『黒い瞳』、『太陽に灼かれて』『シベリアの理髪師』などで知られるロシア映画界の匠、ニキータ・ミハルコフ。ローズの脚本の骨子を忠実に活かしながらも、現代ロシア社会の抱える価値観の混乱、多民族国家ならではの偏見を鋭く抉り出し、エンターテインメントのかたちのなかに、21世紀ならではのドラマに仕上げている。 
チェチェン人の少年がロシア人の養父を殺害した罪で裁判にかけられる。目撃者もあり、容疑は明白。さまざまな分野から任意に選ばれた陪審員たちも審議はかんたんに終わると思われたが――。もはやオリジナル作品の時代のように、社会正義を鼓舞するほどイノセントではなくなってしまった世界を前にしながら、ミハルコフはそれでも人間に対する希望を失っていない。オリジナルでヘンリー・フォンダが演じたような確固たる信念をもった存在ではないが、それでも良心を持ち合わせた陪審員の異議から圧倒的な有罪支持派の11人が論議を尽くし、次第にそれぞれの生活、偏見、予見が浮き彫りになっていく。表面的な自由主義体制になったあげく、経済至上の風潮が跋扈するあまりモラルを失ってしまったロシアの人々の混乱、失意が、緊迫のドラマに貫かれている。